第八話 遠い日の焚き火
都会で育った団塊世代に限って言えば、都会を「故郷」として語れる最後の世代なのかもしれない。
昭和三十年代は、都会が、かろうじて自然を許容していたからである。
物的な景観がどう変わろうと、故郷は故郷であるに違いないだろう。
だが、子どもたちがこころを許しやすい自然風物が、生活の邪魔者としてすでに放逐されてしまっていたなら、子どもたちは故郷のイメージをどう定着できるだろうか
。 「目をつぶると懐かしい故郷の姿が浮かんできます。隅々までアスファルト舗装がなされ、雑草一房も生えていない道路!完璧に護岸工事され、立ち入り禁止となっている河川!判で押したように類似した家並と、角地にあるのはセブン・イレブン!周囲は遠くまで、高層ビルが連なり・・・」
というのが、故郷紹介のスピーチであったなら、誰もがうなずきこそすれ、また同じだ!とげんなりするのではないだろうか。
アスファルト以前の街の情景こそが、故郷についての話にもなれば、ひとを慰めもするのである。
完璧性、危険性など眼中にもなければ念頭にもない、無造作で奔放な、そんな自然のかわいらしさに彩られた情景こそが、故郷の実体ではないかと思う。
また、その情景は、共にあった当時の人々の生き方、感じ方などを随所に編み込み、奥行きをかもし出していることが、またまたうれしいわけなのである。
情景が、完璧性などを眼中に入れていなかった時代には、人々ももちろん完璧性などどこ吹く風といった調子であった。非の打ち所だらけで、かわいらしく生きて、歩いていたと言える。
まるで猫のようであるが・・・
猫と言えば、馬が歩いて、いや歩かされていたことも覚えている。
八ツ山下通りがまだ舗装されていなかった頃、強い風の日には砂ぼこりで十メートル先が見えなくなることもあった。そんな砂ぼこりの中から、突然、二、三頭の馬が視界に飛び込んできた時は、うれしさと驚きがこんがらがってしまったものだ。
さらに、通り過ぎ、次第に遠のく馬たちを眼で追っていた時、中の一頭がボタボタと痕跡まで残していったのには参った。
しかし、だれが騒ぐというわけでもなく、だれが後始末をしたわけでもなかったように思う。
散歩の犬たちの痕跡に目くじらをたてる現在からすれば、まるでうそのような話である。
さて、道路がアスファルト舗装であったか、なかったのかを思い出す有力な方法は、焚き火の思い出だと思う。
道路での焚き火の思い出があれば、幸い(?)にも舗装はされていなかったと言えそうである。
そして、焚き火の思い出があれば、故郷の思い出のひとつや、ふたつは語り切れるはずである。
どういうものか、焚き火というものは、人の身体を暖めるだけではなく、人のこころまで暖かく包んでくれた。
薄ら寒い薄暮の街角に、遠く明々と焚き火の光景が目に入ると、なぜかほっとした気分となった。で、思わず急ぎ足となり、焚き火を目指してしまう。
「あたらせてください」
と、軽い挨拶を添えれば、
「どうぞどうぞ」
という寛大なことばが返ってくる。
談笑し、顔を火照らす人たちは、酒を飲まずとも十分に酔っていたりする。
場合によっては、見ず知らずの者に、焼き芋なり何なり、皆で賞味していたものをお裾分けまでしてくれたりもした。
焚き火は、故郷というものを、明々と、そして豊かに表現する存在以外のなにものでもなかったと思われる。
少年が六年生の時に描いた四ツ切り画用紙の水彩画が、ある時、職員室に飾られたことがあった。
『一意専心』なり、『真実一路』なりの重々しい四字熟語の達筆を収めた額が掲げられるのが常である、職員室正面の壁に、額に入れられてありがたそうに飾られたのであった。
少年は、誇らしくもあったが、その扱いにどんな意味があるのか分からず当惑もした。
その題材が、焚き火なのであった。
確かに、少年はその絵を楽しく、気分上々で、あっという間に描き上げたものだった。
冬の朝の登校は、寒さと眠さで子どもでも気分がめいる。しかし、少年を励ましてくれるものが、途中、品海橋を渡る直前にあった。
八時半過ぎ、ちょうど少年が品海橋に差し掛かる頃、道路わきの空き地で決まったように焚き火をする家族があったのだ。
家族総勢で海苔養殖業を営んでいるようであった。
「また、あたらしてください」
「ああ、いいよ。学校に遅れないかい?」

「走るから、大丈夫です」
「こいつも、早くあんちゃんくらいに大きくなってくれるとありがたいんだけどねぇ」
息子さんらしい人が、ねんねこばんてんから顔を出す赤ちゃんを指差した。
そして手にしていた板切れを焚き火にくべた。パチパチと火の粉が立ち上がった。
「何言ってんの。まだまだこれからだっていうのに、ねぇ」
と、お嫁さんらしい人が、ねんねこと焚き火で顔を火照らせた赤ちゃんに向かって話しかけた。
赤ちゃんは、『そうだそうだ!』とは言わず、ただ満足そうにうつらうつらしている。
お母さんらしい人は、そんな会話を楽しそうに聞き、赤ちゃんの肌着のようなものを、焚き火にかざして暖めていた。老いた雑種犬が、傍に寄り添って寝ている。
焚き火に大きくごつい両手をかざしているのは、手ぬぐいで鉢巻をした、てかてか頭の親父さんらしい人である。
この暖かさに包まれた空間のすべてのすべてに満足しているといった心境が、満面の微笑みから想像できた。
たぶんこの家族は、早朝の品川沖で海苔養殖の一仕事を終え、こうして暖を取っていたに違いなかった。一仕事後のくつろぎといった、充実した空気が充ちていた。
この後の仕事は、生海苔をまきすに張り、天日干しのために、それらを畳一畳ほどの枠にはめ込む作業が待っているはずだった。
そして、少年が下校する頃には、焚き火があった空き地は、一面海苔の天日干し大展覧会となっているはずなのだった。
こうした冬の日の毎日繰り返される実感を、少年は焚き火の絵に塗り込めたのだった。
それは、少年にとっての故郷の貴重なアングルであったに違いなかった。
結局、その絵は少年の手元には戻ってこなかったため、その後時々ふとしたことでその絵のことを思い起こすのだった。
考え過ぎなのかもしれないが、ひょっとしたら、当時の職員室は意外と寒々として、ぎくしゃくしていた時期だったのかもしれないと振り返ったりした。
そうした大人の先生たちの緊張した空気をいくらかでも和らげるべく、子どもの暖かい雰囲気の絵が必要だったのかもしれないなぁ、という想像もした。
もちろん当時の少年の視野には入らなかったはずだが、ちょうどその年は、「六十年安保」が強行採決された年、デモ隊の樺美智子さんが死に追いやられた年、そして西田佐知子のさみしい歌「アカシアの雨がやむとき」の流行った年なのであった。
かろうじての記憶として、あの馬が歩いていた舗装以前の道路を、長い列のデモ行進がゆっくりゆっくりと進んでいた光景を不思議に覚えているのである。
何か特別な切実さを訴える空気に、『これは一体何なのだろうか?』と思い、記憶の懸案箱に仕舞ったままとなっていたのであろう。
考え過ぎに、さらに輪をかけるなら、この年を経て、日本の政治・経済はもっぱら米国よりとなり、社会と生活全体がアメリカ的合理主義に急接近して行ったのかもしれない。
良いも悪いもなく、生活に対して合理性のチェックがなされてゆき、道路のアスファルト舗装工事にしても、当然のごとく推進されていった。
生活のための完璧性が追及されてゆき、街々から、かわいらしさが放逐され、故郷としての柔らかきものの大半が、コンクリートや規格へと迅速に置き換えられていったのである。
また、アスファルトやコンクリートに置き換えられていったのは、都市内部にとどまらなかった。
都市の膨張傾向は、都市周辺をも新興住宅地として、かわいらしさとは無縁の人工物で容赦なく置き換えていったのである。
昭和三十年代は、そうした開発が急展開した時期なのであった。そして、後年、多くの団塊世代が、都市周辺新興住宅地へと移動することにもつながってゆく。
また、規格と完璧性が当初から貫かれて形成された街である新興住宅地は、やがて登場する団塊世代ジュニアたちに対し、親世代とはまったく異なった故郷観を提供していくことになるのである。
ところで、私には、焚き火と故郷をめぐるもうひとつ別な思い出がある。
「にいちゃん、ほら、こっちのが解けて、焼けてきたから喰えるべぇ」
「はい、すみません」
「こねぇして、砕いてけば、ほらな、あっちこちに足があるだべ」
目黒川河口の川岸のコンクリートの上で、二人は凍える身体を癒す焚き火をしていた。
東品川にある水産会社の冷凍倉庫の前である。
大学生の当時、鉄工所でのアルバイトが途絶えた時、私は日当で支払ってもらえる肉体労働のアルバイトに就くことがしばしばあった。
早朝に高田馬場にたどり着けば、「立ちんぼ」という、学生にとっては割のいい土方仕事があったのだが、アパートのある大森町から遠くて間に合わないことが多かった。
比較的近場ということで、故郷品川の「冷凍倉庫霜取り作業、日払可!」が目に入った。むし暑い梅雨時、居心地悪い部屋で新聞記事を見つけた限り、
『こいつは、涼しくていいぞ!』
と飛びついたのだった。
しかし、「日払可!」で募集広告を出すだけのことはあって、ほとんど北極、南極の世界、零下三、四十度の空間での作業なのであった。
防寒服、防寒靴、防寒手袋で身を固めても、息をすると胸が痛くなる低温であった。
シャベルを使って、冷凍倉庫内の壁や管の霜を掻き落とす作業は、呼吸がまま成らないためか想像以上にこたえた。
相棒となった年配の人といっしょに、10分程度の作業しては、表に出て身体を解凍(?)するといった作業パターンを繰り返すのだった。
掻き落とした霜や氷は、表に出る際に、工事現場などで活用されるねこ車に積んで、外にあったすぐ脇の目黒川に捨てるのである。そして、川岸真際の焚き火で暖を取ることになっていた。
冷凍倉庫に収められた荷が、もっぱら蟹であったことが、唯一の慰めとなった。
倉庫内では、気にする程の余裕がないのだが、川に捨てる前、焚き火のそばで確認すると、白っぽく凍った霜の塊の中に、蟹の足が収まっていたりするのだった。
もう長くこの作業を続けている年配の相棒さんは、この役得をしっかりと見逃さなかったのである。
「火の中で解けて、焦げるくれぇがうめぇな」
「じゃあ、こいつはまだですね」
二人は、あまりおおっぴらにはできない小さな焚き火をはさんで、蟹の足をほうばりながら凍りついた身体を暖めていた。
土方現場では、相手のことをあまり聴かないのが鉄則だったので、さり気ない話しかしない私だったが、年配の相棒さんが、にわかに身の上話を切り出し始めたのだった。
------- 郷里の青森から、東京に出てきてもう三年になる。
あっちこっちの工事現場を渡り歩いたけれど、独りで黙々とやれるここの仕事がえらく向いているようだ。寒いのには慣れているし、何より、うるさい現場監督のいないのが気に入っている。
東京は、皆が自分のことで忙しいのか、他人のことを放っておいてくれるから気が休まる。
だけど、年末年始の寂しさが辛い。
誰にも話せないのがさらに辛い。
何と言っても、あと二年は、青森に戻れねぇから。
もともと、東京へ出てきたのは、選り好んでなんかじゃない。
四年前、青森で、飲んでつまらないことがきっかけになって、はでな喧嘩をしてしまった。
それで、人をあやめてしまい、刑に服し、出所した。
ところが、突然、親戚の者たちが、『あと五年、村のうわさが消えるまでは、東京に身を置いてくれ。』と頼みにきたのだ。
最初は断った。だけど、家族に、おまけに娘にまで泣いて懇願されてしまったんだ。
家族の食扶ちを稼ぐ出稼ぎなら、大えばりなんだが、これは体のいい懲役の延長でしかない。
そんなことで、知り合いも何もないというのに東京に、この年で独り出てきたんだ・・・
とつとつとして話し終えた時、赤ら顔の年配の相棒さんは、窪んだ細い眼に、涙をにじませていた。
自分で撒いてしまった種とは言え、故郷からはじき出されてしまったことの寂しさなのか、悔しさなのか、それでもなお募る望郷の念なのか・・・
もちろん私は、何のことばも差し挟めず、じっと焚き火の火を見つめるだけだった。
私は、もう、目の前の焚き火に、あの海苔養殖の大家族たちの焚き火が秘めていた「すべてのすべてに満足」といった無限大の寛容さや楽観性を見出すことが、何か空々しく思え始めていたのだった。
相棒さんは、ひょっとしたら、自分だけを除外しなければ成り立たない故郷とは一体何なのかと問いたかったのかもしれないと思った。
焚き火は、かろうじて、遠い故郷を思い出させ、見ず知らずの相手にこころの中の辛さを覗かさせる、そんな魔力だけは秘めてはいた。
しかし、故郷それ自体でもあった大らかで豊かなそんな焚き火のイメージは消え、それは、もはや手を伸ばしても届かない程に、遠く遠くに霞んでしまっていると確信した。
足元で燃えていた焚き火は、凍った蟹の足を淡々と解かしながら、チリチリという小さな音をたてて、いかにも頼りなく、無力に見えたのだった。
もう、焚き火が故郷そのものであった時代は、遥か遠くで燃え尽きてしまっていたのだった。少なくとも私にはそう思えた。
団塊世代は、少年時代に、都会に残された自然とこれと共存しかわいく生きた人々を、それが故郷だとして幼き脳へ刻み込んだはずである。
ちょうど、鳥たちが、ひなにかえる時、一番最初に眼にした動く存在を親だとして慕う、そうした脳への刷り込みがなされるという事実のように。
そして、たとえその後、時代と環境がどんなに近代的で、画一的で、規格的なものへと変貌していこうとも、その故郷のイメージを焚き火などの象徴に託して、とりあえず抱え続けたに違いない。
いやむしろ、眼の前の実体としては日毎に失われていくこととなった故郷のイメージは、居場所を失うことで、その分美化され観念性を色濃くしていったのかもしれない。
と言うのも、故郷のイメージを押しのけ、遠ざけてゆこうとした環境変化の動きは、速度も速く、範囲も全面的であったからである。
あっという間に土の道路は覆い隠され、アスファルト道路には走り過ぎてゆく車が急増した。もはや道路は、地元の子どもたちの遊び場ではなく、より大掛りな経済の一環になっていった。
暇であることが特権の子どもたち自身も、やがて塾通いの一般化などによって、大人たちのように時間に縛られた存在に変貌させられていった。
海苔養殖が、より大掛りな経済の一環であるアスファルト道路建設のため川が埋め立てられ、廃業に追い込まれてしまったこと。その結果、故郷の景観が大きく変わっていったことも、瞬時の間の出来事であったのだ。
従来から人々が慣れ親しんできた漠然とした存在は、目先の具体的な便利さへとどんどん置き換えられていったのである。
いま思えば、昭和三十年代がもたらした変化というのは、人が生きてゆく時の流れ全体を指した含蓄あることばであった「人生」が、小刻みな要素である合理的な日々の「生活」という単位へと、限りなく分解されていった、そんなプロセスであったように思えてならない。
そして、食品その他、様々な商品や、メイド・イン・USAのテレビドラマなどが、その小刻みな要素の毎日を、退屈にさせなかったどころか、人生の次元とは異なった次元での手頃な充足感で埋め尽くしていったと見える。
やがて、団塊世代は、こうした手頃な充足感で充たされた日々の生活を、これからの自分たちのライフ・スタイルだとして承認していくことになったのであろう。
しかし、ここで奇妙な問題が発生するのである。考え方、感じ方、生き方の二重構造である。
たとえば、団塊世代ジュニアたちにとっては、故郷など初めからなかったと言ってよいだろう。少なくとも、団塊世代以前の者たちが抱く故郷はすでに消滅していたはずなのだから。
しかし、団塊世代は、一方で故郷の実体を少年時代に体験し、故郷のイメージを抱きかかえ続けた。そして、他方では団塊世代ジュニアたちと同様に、もはや故郷を必要としない(?)文化や時代への適応を選び、歩んだのである。
この点は、いわゆる戦中派世代の問題にやや似ているかもしれない。
戦争中に、まだ少年として戦争に「参画」できず後衛であることを余儀なくされた世代が、奇妙に戦争を観念化し、美化して、戦後の価値転換の経過においても、その考え方、感じ方を引きずっていったという話である。
戦争に実質的に駆り出され、戦争の惨さを全人格的に体験した世代は、戦争を美化することなどは決してできなかった。
それに対し、戦争を距離を置いて垣間見た少年たちは、これとは異なった記憶とイメージを抱え続けたというのである。
そう考えると、団塊の世代は、自然や自然的な人間関係という故郷イメージの実体の、上澄みだけを体験して美化しているのだと言うこともできるのかもしれない。
実際、自然は優しさだけではなく、その凶暴な牙をむき、人々を襲うこともあるからである。
また、海苔養殖の家族にしても、すべてに満足どころか、内心では辛いことも、家族間の軋轢も少なくなかったのかもしれない。
だが、そうだとしても、団塊世代が二つの時代にまたがって生きたことに変わりはないだろう。
そんな団塊世代にとって、すべてを時の流れに逆らわず、淡々として日々を消化してゆく限りにおいては、何の問題も自覚されることはなかったと思われる。
現に、この長い不況前までは、自分たちの生活スタイルになんら疑問を投げかけることはなかったに違いないからである。
しかし、現在、ふとしたことから、要素としての日々の生活の虚しさに気づき、自分の人生の意味を確認しようとするや否や、たとえようのない挫折感に苛まれたりする。
あるいはまた、故郷を必要としない(?)文化を大前提として生きている若い世代や、また専らこれにターゲットを合わせた商品文化との間に、何か激しい違和感と軋轢を禁じえない時にも、同様の心境となるのではなかろうか。
故郷や、自然という実体とともにあった泥臭い信念や理想は、口にしたり、憧れたりすることはあっても、それに寄りすがって生きるに耐える形では持ち合わせていない自分たち。
かといって、一度は身を託した完璧性指向の生活スタイルや路線は、今や幾何級数的な舞い上がり方で、人工物というより、サイバーな世界構築へと突き進んでしまって、とても手におえない予感が満ち満ちてしまう。
これらのどちらにも、思いを託して身をまかせてゆくことができない団塊世代。
逆に言えば、両者のハイブリッドとして、時代の接着剤、インターフェイスにも、なろうとすればなれた存在でもあったはずなのだ。現に、一時は、時代のリーダーと目されてもいたのであったが・・・
要するに、死活に類する程の問題に直面した際の、全体重をかけて判断する時の根拠において、どっちつかずで、中途半端な二重構造的な脆さを持ってしまっているのが、団塊世代ではないのかと気付かされてしまうのである。
そして今、団塊世代を含め多くの人々が、まあいいかと流してしまうには辛すぎる問題だらけの状況に遭遇しているのではないだろうか。
昭和三十年代から加速していった生活の変化のカードが、ほぼ出揃ったところで迎えている現状は、誰の予想にも反し、あまりにもひど過ぎるからである。
「あまりにもひど過ぎる」の実体は、前後は言うに及ばず、左右も真っ暗な、そんな出口無しかと見える暗闇に国民こぞって迷子になってしまったような現状のことである。
気掛かりな問題が、不況だけでないことは多くの人々がとっくに感づいているようだ。
不況によっていろいろな問題が増幅されているのは事実だと思われるが、逆にいろいろな問題が原因で不況の脱出口が遠のいていることも事実だと思われる。
度し難い政治の貧困がまず挙げられるが、むしろ、さまざまな分野での人間関係が無惨な壊れ方をしている問題が、無視できないと思われる。
それは、その行き着く先で生じる現象としての犯罪に限られることではないはずだろう。
職場を初めとして、人間関係で成り立つあらゆる集団や組織が、機能不全、関係不全、肝硬変(?)に陥っていると言われている。
長い眼で見るなら、それはそれでいたし方ないのかもしれない。先の相棒さんのような部外者を作り出すことで、かろうじて成立するようなまとまりは、本物とは思えないからである。
それにしても時の趨勢は、不況に起因するリストラ実施で、ますますこれまでの日本のお家芸であった集団主義を背後に引っ込めて、かたち優先の格好で、個人主義、能力主義に肩入れし始めている。
しかし、現在、その個人主義の風潮が、人々に感じさせているのは、本来のそれではなく、否定的な意味で「ジコチュウ」と呼ばれる自己中心主義でしかないように見える。
世間体を初めとする集団性以外にこころを縛る原理が持てずにきたわれわれが、突如として世間を遮断する様々な個人生活環境----- 職場では、壁で囲まれた個人ブースが大流行である! -----に突入すれば、どうなるのかの必然的結果なのかもしれない。
さらに皮肉めいた表現をすれば、現在の「ジコチュウ」は、高度経済成長の推進役であった企業中心主義、職場中心主義と言った集団・組織的「ジコチュウ」の解体結果なのかもしれない。その集団・組織的「ジコチュウ」を支えたのが、団塊世代であったのだが。
いずれにしても、大人たちのジコチュウは、それが悪いと知りながらも、『こんなご時世、こうでもして生きてゆかなければ、生き残れない!』とばかりの「開き直りジコチュウ」であろうか。
また、若年世代は、そもそもそれが悪いと自覚する視野や基準を持たない「純正ジコチュウ」と言える実態なのかもしれない。
今後の人間関係のあり方は、個人主義に基づく個人と個人の連携、あるいはネットワークという形式しか残されていないはずである。
遠い日の焚き火のイメージが照らす「餅」のような同質一体型人間関係は、どんなに夢の中で憧れても、もはや絶対に再現されることはありえないだろう。
逆に、人為的なそんなものが何かのはずみで強制されることが、もしあるとすれば、とんでもないことだと思えるのだが。
それにしても、いらだつ気分が生じるのは、われわれの目の前にうずたかく積まれている難問、例えば、少子高齢化、巨大な財政赤字、そしてカウントダウン的な危機に直面している環境問題などが、今後個々人が共に手を携え合ってゆかなければとうてい解決できない課題ばかりだからである。
これらのリアルな難問に眼をむけるなら、個人の自由拡大への一里塚なのだからまあまあと言って、「ジコチュウ」現象をいなす気持ちにはなれないであろう。
そして、「純正ジコチュウ」の若年世代に拍車をかけたのが、集団・組織的「ジコチュウ」にはまり込んでいったり、または中途半端な思考スタイルで毅然としえない団塊世代であった、あるいはである点から眼を逸らすことはできないと思えるのである。
確かに、ここまで「ジコチュウ」を蔓延させるに至らしめたのは、誰々という人間に原因があるという以上に、ここまで成長してしまった恐竜のような経済システムの仕業であると言うのが正確かもしれない。
故郷だけでなく、人間自身をも含む自然や、あるいは誰のものでもなかった人々の共有財産であったものが、巧みに切り刻まれ、いつの間にかこの市場経済システムに組み込まれていったのだ。
商品化できるものは何でも商品化するといった経済システムと、われわれの経済生活が、「ジコチュウ」の発想のしたたかな基盤をしっかりと形成してしまった、と言っても言い過ぎではないであろう。
なぜと言うに、支払うべき対価さえ持っているなら、さしあたって個人を万能に仕立て上げ、煩わしいと思えば他者との関係を限りなく省略、排除可能とするのがこの経済システムの原理だからである。
自販機や通販を思い浮かべるだけで、その仕組みは実感できるし、想像できる。大人はもちろんのこと、青少年であってもそうなのである。
なお、この進展は、昭和三十年代から急速に立ち上がり、多くの荷担者を巻き込みながら、凄まじい様相を呈する現代に、綿々と連なって来たのである。
現在のインターネットなどのITの道具立ては、このシステムのプラスマイナスの両面をとてつもない規模で増幅しているのである。
ただ、この経済システムの進展についても、団塊世代が消極的、積極的の差こそあれ、概ね荷担してきたことも、否めない事実なのである。
これらが、団塊世代の責任を感じると言い添えた中身である。
地獄への道は、善意によって敷き詰められている、との皮肉なことぱがあったように思う。
団塊世代の善意など、誰も信じないであろうが、経済の発展やアメリカナイズされた生活への接近が、皆の幸せを可能にすると無意識に承認したことの「つけ」が、今朝の郵便箱に入っていたようなイメージではないだろうか。
昨今、教育基本法の変更、奉仕活動の義務化などへの動きが見受けられるが、そんな気休めの方策で済む問題ではないばかりか、事態をこじらせるだけのように思えてならない。
むしろ、今後も付き合うしかいたし方のないこの恐竜のようなシステムの首根っこに、人の血の通った目立つ黄色い鈴を、どのようにかしてぶら下げてやるのが、当面のブレーカーであり、リベンジ(!?)だと勝手に信じているのである。もちろん、団塊世代が自分たちの弱点を克服しつつの話であるが・・・
 二人の子の夏休み中に移動をし、九月の新学期から転入するのが良策だと配慮された結果だった。
二人の子の夏休み中に移動をし、九月の新学期から転入するのが良策だと配慮された結果だった。




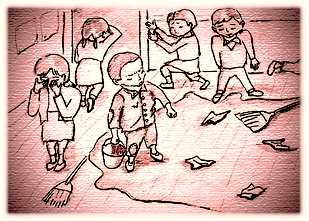





Kamome_iPad.gif)
Kamome_iPhone.gif)









