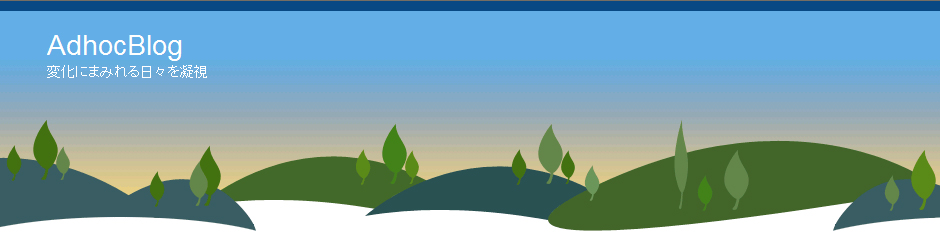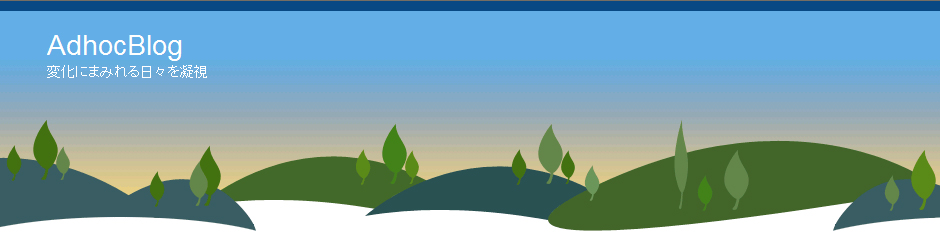�@�ȑO�ɁA�M��w�͂������q�x�i �n�쏭�N���w�E�ߓ�������A�c���ēA�ؕ�����A�L�n��q�o���A�P�X�U�P�N��i �j�ɂ��ď������B
������͏��w�������Ɍ�����f����Ƃ��Ɋӏ܂��Č��C�Â���ꂽ���̂ł��������A���̓����̂Ȃ������������i���܂��Ƀ��A���ɉf���Ă���̂ɂ͂��ꂵ�������ł������B���ƁB
�@�m���ɂ����Ȃ̂ł��邪�A�����͑����̂�т�Ƃ����C���ɔC���Ă��̃r�f�I����������Ɗӏ܂��Ă݂��B�����āA�Ɋ��������Ƃ́A���̍�i�Ɏc��A�c�O�Ȃ��猻�݂̂��̍����玸���Ă��܂������Ɍ�������̂́A�����P�Ɂ������̂Ȃ������������i�������ł͂Ȃ��������A�Ƃ������Ƃł������B
�@���́A���̍�i�́A�P�ɕ��S�������ƂɂȂ�Ȃ��猳�C�ɐ����悤�Ƃ��鏭�N���߂��镨��ł��邾���łȂ��A��x�ƔߎS�Ȑ푈�������N�����܂��Ƃ��铖���̐l�X�̊肢�ƌ��ӂ����߂�ꂽ�i�������f�悾�����̂ł���B���̏��Ղ��ۉ��Ȃ���������ɂ���Ȃ�����A��㖯���`�̏��X��������̑O�����ȋ�C�A���̕����ƁA�푈�ދC���Ƃ��A�܂�ŐV���f����悤�ɑS�҂ɂ݂Ȃ����Ă���B���̙{���ʂƌ�����قǂɑO�����Ȉ�ۂ́A�u���т�Ă��܂����v���ɂ������錻�݂̂���ꂩ�炷��A�����C�p���������C�������������������ɂ͂����Ȃ��قǂ�������Ȃ��B
�@�܂�A���a�R�O�N��ɂ͂����āA���ݎ����Ă��܂�����������Ȃ����̂Ƃ́A�P�Ɂ������̂Ȃ������������i�������ł͂Ȃ��A�^���ʂ���푈�̍ė��������Ȃ��Ƃ������̋C���ƌ��ӂł͂Ȃ��̂��Ǝ��₵���̂ł������B
�@�����̔���ӎ��́A�푈�Ŕ�Q�����s�K�Ȑl�X�̎����ƁA���a���@�⍑�ە��a�^���Ƃ��������f����ꂽ����ɂ���Ď�����Ă����ƌ�����B���̉f��ł��A�푈�Őe��S�������q���������O�҂�\�����A���l�X�R���ւ̉����Ƃ����ے��I�ȏ�ʂ��A��҂������Ɏw�������Ă���B�t�m�d�r�b�n�iUnited Nations Educational,Scientific,and Cultural Organization ���A����Ȋw�����@�ցB����E�Ȋw�E������ʂ��ď����Ԃ̋��͂𑣐i���A����ɂ�蕽�a�ƈ��S�ۏ�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�ɁA1946�N�ɐ����j�́A���ە��a���i�̒��S���鍑�A�̂ЂƂ̏d�v�Ȋ�ł������͂��ł���B
�@�O�҂ɂ��ẮA�푈�̌��́u�����v�Ƃ�����Ȃ����Ԃ��L������邵�A���ە��a�^���ɂ��Ă��A���̃��[�_�[�i�ł������č����̂����A�͉������铮���ɏo�Ă��܂��قǂɍ������Ă��܂��Ă���B
�@���݂̓��{���{���A�ǂ�ȑ�`�������f���Ă���̂��͉��Ƃ������ɋꂵ�ނ̂ł��邪�A����Ȃ��Ƃ������āA���j�Ղ����������Ɍ����ĂȂ�Ȃ��č��̊O���p���ɏ�����グ�Ēǐ����Ă���B���̋���ɁA�����̑���ȋ]���̂��Ƃɓ��B�����u���a���@�v���u�����v���郊�A���Ȓi���𒅁X�Ƃ��艟�����Ă��邠�肳�܂ł���B
�@���łɁA���̌��ӂƂ��̑̐��́A�����D�ق���͂��߂Ă���A����A�u��b�H���v�͂��炩���ς�ł���Ȃ̂�������Ȃ��B�u�����Q�q�v�Ȃ��Ƃ����̂̓A�i�N���j�Y���ȊO�ł͂Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA�܂��Ƃ��₩�Ȋ�����Ă��̃p�t�H�[�}���X�������Ă���҂́A�P�Ȃ�l�I�Ȓ��ˏオ��Ȃł͂Ȃ��B��������Ɓu���n�t���v�Ȃ���A�u�������A���|���e�B�b�N�X�v�̃��[���𑖂��Ă���ɈႢ�Ȃ��ƌ����ׂ����낤�B�u�����Q�q�v�́A�u���q���̌�팠�v�Ƒ��Ȃ��A�u���a���@�v���e�R�ȊO�ł͂Ȃ��͂����B�����Ă���炪�A���͂�t�B�j�b�V���I�@�����ߍ��ސ��O�̂Ƃ���ɂ܂ŗ��Ă���Ƃ����̂ɁA������Î����Ă��鍑���͂����قǑ��݂���̂ł��낤���c�c�B
�@���ꂪ�A�O�q�́A���a�R�O�N��̖M��̋L�O��I�f��̂ЂƂł���w�͂������q�x�ɂ͖��ł��Ă������A���͂⎸��ꂽ�ɓ������Ǝc�O�Ɏv���_�������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�����Ƃ������j���A��p���f�����}�X�E���f�B�A�A���{���v���f���[�T�[�̃}�X�E���f�B�A�́A�O�_�Z�b�g�ō��������҂��͂����ނ悤�ȃA�N�V�������J��L���Ă�����ۂ����B
�@���̂P�A�u����t�@���h�v�������㎁�ɑ{���̎肪�y��ł��邱�Ƃ�A���͌����Čo�ς́u�s�߂����v���R��`�������Ă͂��Ȃ����A�Ƃł��A�s�[�����Ă��邩�̂悤�Ɍ�����̂������B
�@���̂Q�A�u�H�c���̒j���E�Q�����v�Ɋւ��āA�u�C�Ӂv�̒i�K�ł���Ȃ���Ƒ�{���ɋy���Ƃł���B�����ł��A�����̗���Ɍx�@�͒x����Ƃ��Ă͂��Ȃ��Ƃ����A�s�[�����Ȃ��ꂽ���Ɏv�����B�Ȃ��A�u�C�Ӂv�̒i�K�ŁH�@�Ƃ����_�ƁA�Ȃ������Ƃ������j���łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ������ƂȂ̂ł���B����s�����A���R���A����Ƃ��c�c�B
�@���̂R�A�����Ɩڂ����u�����v�����A��������e�ǂ̕ԑg�Ő��o�����āA��X�I�ȃL�����y�[�����Ă����B�^�J�̉�ۏo���̌������ɂƂ��āA�ǂ����Ă����̌�p�҂͂�͂�^�J�̎q�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��낤�B���̃A�s�[���́A���ƌ��́u���݁v�������ł����L��_�Ƌ��������ĂȂ����̂���X�ƒN�����l�����Ƃ��Ă��킩��ʂł͂Ȃ��B
�@�܂��āA���T�Ƃ��Ȃ�A�����̊S�͐����ȂɏW�܂�悤���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B�u���[���h�J�b�v�v�̃o�J�������n�܂�ł��낤����c�c�B����ɂ��Ă��A�}�X�E���f�B�A���Ƃ��Ƃ��g���錻�݂̐�����忂��̓n���p�ł͂Ȃ��C�z��������c�c�@(2006.06.04�j